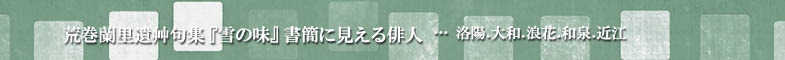
HOME≫DATA≫『雪の味』書簡にみる俳人地域一覧≫洛陽など
井上重厚 柏原瓦全 勝見二柳 沂風 横沼素兄 中西馬瓢
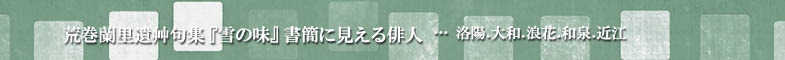
HOME≫DATA≫『雪の味』書簡にみる俳人地域一覧≫洛陽など
井上重厚 柏原瓦全 勝見二柳 沂風 横沼素兄 中西馬瓢
| 井上重厚: 1738-1783 江戸時代中期-後期の俳人 <いのうえ じゅうこう> 元文3年生まれ。京都の人。五升庵蝶夢(ごしょうあんちょうむ)の門人。明和7年(1770)京都嵯峨野(さがの)に向井去来の落柿舎(らくししゃ)を再興して住む。全国を行脚し、寛政4年近江(滋賀県)粟津(あわづ)の義仲寺住職、無名庵主。同5年芭蕉百回忌を営む。 享和4年1月18日死去。67歳。姓は別に菅原。号は落柿舎、椿杖斎。編著に『落柿舎日記』など。 柏原瓦全: 1744-1825 江戸中期後期の俳人。 <かしはら がぜん> 延享元年生まれ。京都の今出川、八条殿町などに住んで京扇の商いに従事。国学を伴嵩嗘蹊に学び、俳諧は蝶夢に師事した。ことに師を敬する情あつく、蝶夢の遺書『俳諧童子教』『蝶夢和尚文集』を出版したり、松尾芭蕉、蝶夢の句碑を建立したりして、顕彰に努めた。著書は多く、『職人尽発句合』や自身の文を集めた『根無草』などがある。 勝見二柳: 1723-1803 江戸時代中期後期の俳人 <かつみ じりゅう> 享保8年生まれ。泉屋桃妖、和田希因に学ぶ。蕉風の復興を説いて全国を行脚。二条家から中興宗匠の称号をあたえられた。享和3年3月28日死去。81歳。加賀(石川県)出身。名は充茂。別号に二柳庵、三四坊。著作に「吉備吟草」「俳諧夜話」など。長男、桃処、不二庵。 沂風: 1752-1800 江戸時代中期・後期の俳人 <きふう> 宝暦2年生まれ。真宗高田派の僧侶。五升庵蝶夢(ごしょうあんちょうむ)に俳諧を学ぶ。安永7年近江大津の義仲寺無名庵主となり、蝶夢の芭蕉復興運動をたすけて芭蕉九十回忌をおこない、粟津文庫を修築した。寛政12年4月死去。49歳。俗称は塩路。名は琳澄。別号に得往、方広坊、爾時庵。編著に「萩のむしろ」。 西澤芦水: ?-? 江戸中期の俳人 <にしざわ ろすい> 愛知川町の人。通称、孝左衛門。里秋ともに宿駅の事に多忙なる人なりしも、同気相投ずる二人は寛政中、町畔に一亭を建て蝸牛庵と号し、少閑此処に会して廃寺を楽しむ。(近江愛智郡志巻三・人物志) 横沼素兄: 1805-1885 江戸後期・明治時代の俳人 <よこぬま そけい> 文化2年生まれ。周防(山口県)の人。桜井梅室の門人。博多の仙厓義梵(ぎぼん)、尾道の物外不遷(ふせん)、河村公成(こうせい)を友とし、蕉風の復興につとめた。明治18年8月死去。81歳。通称は栄三郎。別号に玉心堂。著作に「奥の雪道」「常異弁」。 仲西馬瓢: 1716-1801 江戸時代中期・後期の俳人 <なかにし ばひょう> 愛知県平尾村(東近江市)の生まれ。生家は彦根藩から桃尾山と池之尻の藩林の管理を任され、苗字帯刀を許されていた。京都で俳諧を学び、後に愛知川宿の蝸牛庵を拠点にして、松尾芭蕉の流れをくむ近江蕉門の一員として、湖東地域でおおいに活躍した。自身でも酔茶亭を開く。寛政12年(1800)の著作『筆の塵』。 |
||